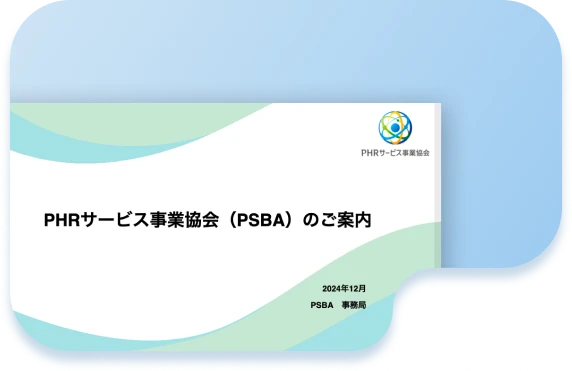会員交流イベントからわずか4ヶ月で事業共創を実現!
2024.12.19
対談者
三井不動産株式会社 柏の葉街づくり推進部 竹川 励(たけかわ れい)様
Arteryex株式会社 代表取締役社長 李 東瀛(り とうえい)様
PHRサービス事業協会 広報委員長/エーザイ株式会社 冨田清行
対談の様子をYouTubeからもご覧いただけます。

2024年9月、千葉県・柏の葉の街づくり組織 一般社団法人UDCKタウンマネジメント(以下『UDCKTM』)が運営しているヘルスケア・ポータルサイト「スマートライフパス」に、Arteryex株式会社(以下『アーテリックス』)の健康管理アプリ「パシャっとカルテ」が導入されました。これは、PHRサービス事業協会の会員交流イベントでUDCKTMの運営者である三井不動産とアーテリックスが初めて出会ってから、わずか4ヶ月で実現したものです。
今回のコラボレーションの内容や、異例なほどのスピードで実現に至った経緯、そして今後の構想などについて、お話を伺いました。
お話いただいたのは、三井不動産株式会社 柏の葉まちづくり推進部の竹川励さんと、Arteryex株式会社 代表取締役社長の李東瀛さん。聞き手は、PHRサービス事業協会 広報委員長の、エーザイ株式会社 冨田清行です。
会員交流イベントの優れた設計により、共創できる可能性の高いパートナーとマッチング。お互いの強みを活かした拡張性の高いコラボレーションを実現
冨田:今日はお時間をいただき、ありがとうございます。お話を進めるにあたって、まず「スマートライフパス」と「パシャっとカルテ」の概要について教えてください。
竹川様:私たちは2006年以来、千葉県柏市にある「柏の葉キャンパス」エリアにおいて街づくりを進めています。そのテーマの1つが「健康長寿」。出来るだけ病気にならず、誰もが健康で長生きできる街を目指しています。「スマートライフパス」は、その取り組みの中心となっている健康サービスのポータルサイトです。独自のデータ連携基盤「Dot to Dot」を基にしているので、ユーザーは複数の事業者のサービスをシームレスに使うことができ、事業者は他のサービス利用履歴からインセンティブポイントを付与するなど、他社サービスと連携することが可能です。現在は、柏の葉のほか、神戸市さんにもご採用いただいています。

李様:当社は2018年に創業したスタートアップです。創業前、私自身が患者として医療サービスを受けてきて、検査や治療や薬のデータが自分の手元で一括して見られない、活用できないことに疑問を感じていました。会社で受けた健康診断の結果も、転職すると見られない。これはおかしい、不便だなと。このペインを解消する手段を探したのですが見つからなかったので、自分で創ることにしました。
「パシャっとカルテ」は、健康診断の結果をはじめとする様々な医療情報・健康記録をスマートフォンで文字通り「パシャっと」撮影するだけで一元管理することが可能なアプリです。すでに70万ダウンロードを達成しています。また、製薬会社・保険会社様、ヘルスケア関連企業様、食品会社様向けに、患者インサイト探索、広告キャンペーン、そしてPHRデータAPI連携など、このアプリを通じて取得したデータを活用したサービスを提供しています。
冨田:なるほど。いま少しお話をうかがっただけでも、「スマートライフパス」に「パシャっとカルテ」が導入されるとお互いの可能性が広がることがイメージできます。
今回の共創は、PHRサービス事業協会の会員交流イベントがきっかけだったとうかがっています。その経緯について、お聞かせください。
竹川様:今年の5月に行われた会員交流イベントで、李社長に初めてお会いしました。イベントの第一部では参加各社がそれぞれ3 分ほど自社の取り組みを説明したので、お互いに組めそうな相手が最初に分かりましたし、なにより熱量が高い方が多いという印象を受けました。こうした交流イベントは正直あまり成果を期待できないものも多いのですが、どうやら今日は違うなと。これは積極的に参加しよう、と第二部の懇親会に望んだんです。そうしたら…あれは確か李社長からお声がけをいただいたんですよね?
李様:はい、そうです。当社は「パシャっとカルテ」の事業実証を進めるためのユーザーや仕組みを持っている企業を探していたんです。確か三井不動産さんは一番最初にプレゼンされたんですよね。それを聞いて、これはぜひお話したいなと思い、懇親会でお声がけさせていただきました。その場ではほんの少し会話を交わしただけだったのですが、さらに具体的にお話を進めたいと思い、その後すぐにあらためて連絡させていただきました。
冨田:竹川さん、この交流会は期待できそうだ、と思われたという、そのポイントはどこだったのでしょう。

竹川様:こうしたイベントでは、どのような方々が何を期待して集まっているのか、そこがとても重要だと感じています。このときのPHRサービス事業協会のイベントには経済産業省の方もいらっしゃると聞いていましたし、もともと一定の期待感はありました。その上で、当日参加された皆さまのプレゼンをうかがって、各組織・プロジェクトにおいて意思決定出来る方、話を進めていける方が多くいらっしゃるなと。この皆さまとなら、具体的なお話が進められるのではないかと思いました。
私は普段イベントにはほとんど参加しませんが、PHRサービス事業協会のイベントにだけは参加するようにしています(笑)
シームレスなデータ連携が可能なプラットフォーム上で、「医療情報のデータ化サービス」と、「医療データを活用した健康サービス」が連携
冨田:ありがとうございます。会員企業のネットワーキングは協会の重要な機能だと考えていますが、それにしても想定以上のスピードで具体的な事業のお話が進んでいくのは嬉しい驚きでした。後日のオンラインミーティングではどのようなお話をされたのですか。
李様:こうした協会や協議会のような集まりでは自社サービスを売り込む営業系の方が多い印象なのですが、当社はブランディング、認知度の向上が課題なので、先ほども申し上げましたが社会実装の機会が欲しいのです。竹川さんにそうしたお話をしたところ、その場でアイデアをいただきました。「そういうことなら、柏の葉でやった方が早いよ」と。
竹川様:こういうケースでは、「一緒に自治体に提案しましょう。私たちの開発費・利用料は…」と、ビジネスなので当然ではありますが、何かの受発注関係を前提に話をする会社さんが多いです。ただ、そのスキームだとどうしても調整や予算化に時間がかかる。今回についてはお互いの利害が一致していたので、最初のミーティングで「お互いのサービスを提供し合って、まずミニマムで開始できるデータ連携から始めましょう」という合意が出来ました。

冨田:その結果、わずか4カ月後の9月から連携が始まったわけですが、その内容は具体的にどのようなものなのでしょうか。
竹川様:まずはシンプルな連携から始めました。ユーザーが医療関係の書類をスマホで撮影して「パシャっとカルテ」からデータ化すると、その「データ化した」という事実=「パシャっとカルテを一回使いました」ということが「スマートライフパス」に送られ、1回につき10ポイント付与される、というものです。書類の内容については連携されません。まずはお互いのユーザーを増やし、利用を促進することを目指しました。
冨田:最初に欲張り過ぎず、まずはすぐに出来ることから初めてファクトをつくる、というのもスピード感のある共創実現のポイントですね。
ここを起点に、今後はどういうことをしていきたいですか。
竹川様:すでに少しずつ動き始めていますが、たとえば疾病リスク予測に基づく健康改善策の提案が出来ると良いですね。登録情報を元に連携サービスのデータから疾病リスクを判定し、食事アドバイスなどをアウトプットするイメージです。
たとえば「スマートライフパス」で提供中の「Health Data Bank」では、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の疾病リスク予測ができ、「カロママプラス」というAI健康アプリと連携することで生活アドバイスにつなげています。 同様に、「パシャっとカルテ」に疾病リスク予測を連携することで、「健診情報を自ら登録することで自分の生活習慣病のリスクがわかる」というサービスをつくることが出来るのではないかと思っています。
プラットフォームの運営者として多くの事業者さんとお会いしますが、優れたアルゴリズムやサービスを持っている事業者の多くが課題にしているのが、医療情報のデータ化の部分です。現在、健康診断結果を読み取って登録する方法はOCRによる画像認識が主流で、これは精度が低く、人の手によって補正していかなければならないのが難点です。一方で「パシャっとカルテ」ではデータ登録が簡単で、かつデータが正確です。サービス側にとって、これは大きな魅力です。
李様:まさに、そこですね。私たちが一番力を入れているのは、「医療情報のデータ化」のユーザー体験をつくっていくことです。と言うのは、ヘルスケア関連領域では、スタートアップから大企業まで様々なプレイヤーが「手元に医療データがあること」を前提にしてそのデータを活用するサービスを展開していますが、そもそもデータ化された医療情報が世の中には多くないんです。そこで当社は、ユーザー自身が手軽に自分の医療関連情報をデータ化できるサービスを開発しました。データ化のプロセスに特化しているという点において、当社は他社とはまったく違うポジションを確立できていると自負しています。
それを踏まえ、これを拡げていって社会的に価値あるものにするためには、当社がデータ化した情報を使ってユーザーに新しいサービスをアウトプットしてくれる提携先の存在が、とても重要です。ユーザーとのタッチポイントが増えれば増えるほど、私たちが医療・ヘルスケア領域で活躍できる幅が広がっていく。「Dot to Dot」というパーソナルデータの連携基盤と、その上で複数の企業のサービスが連携している「スマートライフパス」は、そういう意味でとても魅力的です。様々な事業者さんにより色々なサービスが開発されていくことを期待しています。

多様なプレイヤーが集まり具体的な成果を生み出していくための、実効性の高い場づくりを目指して
冨田: PHRサービス事業協会の設立からわずか1年でこうした事例が生まれたことを嬉しく、ありがたく思っています。今後も、会員の皆さまがメリットを実感できるような、手ごたえのある取り組みを進めていかなければならないと考えています。参加しやすく、かつ具体的に得られるものがあるイベントや仕組みづくり、そして会員の皆さまが発信できる場づくり、そのために、会員の皆さまの声がとても重要です。最後に、協会への期待や、協会の活動へのアドバイスをいただけますでしょうか。
李様:ビジネスパーソンにとって、とりわけ私たちスタートアップにとって、時間はコストそのものです。ですので、イベントがあまり多すぎるのも良くない。PHRサービス事業協会の会員交流イベントは年2~3回とのことですが、これはちょうどいい頻度だと思います。
ヘルスケア・健康領域はマネタイズが難しく、志は高くても儲かっていないところも多い印象があります。たとえば大企業からスタートアップにソリューションを募るような機会があってもいいかもしれないですね。
竹川様:そう、話が具体的な方がいいですよね。大手企業は大きな営業部隊や顧客、場を持っていますので、多くのスタートアップにとって魅力的なはずです。会員の共創事例が多く生まれ、その成果をストーリーとともに語っていけるようになれば良いですね。事例をしっかり伝えていくことで、協会に参加するメリットを可視化する。それが、先ほど申し上げたこうした取り組みの最大のポイントである「意思決定者が参加し続ける」ことに繋がると思います。
また、参加する我々企業側も、お客さん気分ではなく、このような活きた取組を維持するために、「事業共創でこの産業の活性化をするために参加するのだ!」と明確な目的意識をもって参加することが大事だと思います。
冨田:その通りですね。スタートアップや大手企業などの様々な業種・業態の事業者、さらに経済産業省や厚生労働省をはじめとする国も含め、多様なプレイヤーが積極的に交わって具体的な成果を生み出していく。そうした場を皆さまと一緒に創っていきたいと思います。
本日はありがとうございました。