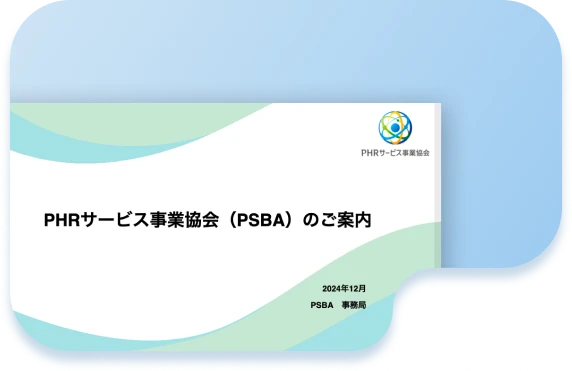PHRサービス事業は健康課題を洗い出し、データを活用して最適なソリューションを創り出すところに活路がある
2025.03.31

デジタル版「おくすり手帳」でPHRサービス事業を展開しながらお薬手帳PHRを活用した運輸業界向け事業の立ち上げ
ーはじめにharmoがどのような企業なのか教えてください。
山東:harmoは、元々ソニー傘下の企業としてデジタル版『おくすり手帳』の事業を展開していましたが、2019年にシミックホールディングスが事業を継承し、2021年から分社化してシミックホールディングスのグループ会社のひとつとなり、一般の方向けの無料アプリ、薬局向けのアプリ、病院など医療機関へのシステムの提供など、誰の生活にも調和するサービスの提供と仕組み作りといったヘルスケアにおける社会課題の解決を目指しています。
―具体的にどのような事業展開をされていますか?
山東:まず、一般向けアプリの『おくすり手帳』は、2008年に開発されたデジタル版としては草分け的存在のおくすり手帳です。紙のお薬手帳は、薬局に行くときに忘れてしまったり、かさばったり、何より長年投薬されている方はお薬手帳が何冊もできてしまうというデメリットがあります。また、薬の登録がシールで行うと時系列に貼られていない場合もあったりする問題も、自動で楽々解決できます。また、アラーム機能で薬の飲み忘れを防いだり、処方箋送信機能で、処方箋をもらったらすぐに薬局に送っておくことで待ち時間短縮できるなどが、紙版とデジタル版の大きな違いです。なお、デジタル版のお薬手帳は、現在数十ブランドほどあり、スマートフォンが普及した現在、デジタル版で利用することで、様々なことが一元化でき、お薬手帳の利便性は向上しています。厚生労働省のガイドラインが発行されており、標準化が進んでいる分野でもあります。具体的には患者さんはどの薬局に通っても共通の二次元バーコードで服薬情報を登録でき、ブランド間の切替などのポータビリティが整備されています。
―まさにPHRサービス事業ですが、マネタイズはできているのですか?
山東:お薬手帳アプリの事業としては、コンシューマアプリと病院や薬局といった医療機関向けアプリの2つのProductで構成されており、前者は無償ですが、後者は月額利用料を頂いています。医療機関からのマネタイズが成立する背景には、診療報酬(薬剤服用歴管理指導料)が電子お薬手帳で算定できる点が強固な基盤となっています。この意味ではマネタイズしていると言えます。ただし、harmo株式会社としての収益バランスから言うと、医療ユースケース単独ではまだまだです。なので、並行してアカデミアや製薬/医療機器メーカーを対象にしたデータ事業、医療ユースケース以外のB2B2C事業の開拓をしています。
―その医療ユースケース以外の事業とはどういうものですか?
山東:昨年11月から運輸業向け事業を新たに展開しました。運輸業、特にドライバーの方の治療習慣をサポートをしていくことで、健康起因事故を防ぐというSolutionでローンチ後に多くの業界紙に取り上げて頂き、既に数社に導入を頂いているサービスです。(https://www.harmo.biz/well-harmo/)
運輸業界では、ドライバーの人手不足や高齢化など社会課題が多々あり、また歴史的に事故防止に向けた運輸安全マネジメント制度という規制など業界活動が進んでいました。特に最近では高齢化から持病を抱えている従業員も増えつつあり、事故防止の観点では健康管理の重要性が増しています。このサービスをローンチする以前に実証実験として、2023年12月から半年間、運輸会社さまにアプリを提供して、ドライバーの治療状況を運輸管理者の方で共有してもらい、治療内容、例えば薬に関する知識の理解度、薬の追加へ変更の把握、通院漏れチェックを行い、必要な方にちゃんと治療習慣を意識づけていきましょうというアプローチをしました。この実証実験を開始した頃は、首都高速でタクシー運転手の方が走行中に意識喪失となり死亡事故が起きたというニュースが話題になった時期でした。車の運転は、ドライバーさんだけでなく事故が起きた近くにいた人、乗客、貨物にも影響が出ます。今働いている方の中には治療中の方もいるはずで、治療中の方には、適切に薬を飲んでもらう、診察に行ってもらう、など治療に対して積極的に関与してもらえる仕組みを作ることで健康起因事故をひとつでも防ぐモデルを作りたいと考え、運輸会社さまのご協力のもとに実施しました。実証実験の結果、運輸会社さま数社で、274名の方にharmoアプリに登録いただきましたが、そのうちの102名が何らかの投薬治療を行なっていることがわかり、さらに約35%の方が運転事故リスクのある薬を服用、約50%の方が運転事故リスクのある疾患を罹患していることがわかりました。また、アプリを通じた服薬管理などで飲み忘れが全くなくなったという方や、服薬し忘れた場合の対応方法を理解したという方が増加するなど、ヘルスリテラシーの向上となる成果を得られ、お薬手帳アプリによる課題解決の手ごたえを感じ、本格的な事業展開をスタートすることにしました。そして、昨年12月に弊社サービスを導入頂いた企業が、ドライバーの服薬管理による安全体制の強化を行なったことで、国土交通省「運輸安全マネジメント有料事業者等表彰」を受賞し、わたくしも表彰式の場に同席させてもらうという恩恵を受けました。(笑)

個人の健康課題の解決ではなく企業や行政の課題を解決するためのPHRサービス事業を
―ずばり、harmoの魅力とは?
山東:日本国民の9割以上の方がお薬手帳というものがあることを知っているし、利用されている方も多いのですが、自分の健康管理のためにお薬手帳を持とう!という方は、正直ごくわずかではないでしょうか?医療のリテラシーが高い人や、薬を服用することがご自分の生活や生命にダイレクトに関わる方は、お薬手帳を上手に活用しようと考えると思いますが、多くの方が自分のためではなく、医療関連での利用してもらうために受動的にお薬手帳をお持ちになっているように思います。一般論になりますが、そもそも日本は、病気になって医療費を払うことになっても国民皆保険によって守られています。海外では医療費が加入する保険により異なるため、病気にならないための投資に意欲的であるという見方があると思います。日本は素晴らしい仕組みがある一方、治療や医療、予防に対する意識が低くなりやすい。この環境を踏まえたチャレンジが日本では必要なのだと思います。harmoは、日本の医療インフラとして定着している『お薬手帳PHR』という基盤を活かし、このチャレンジに真っ向から挑んでいる事が魅力だと思います。『大切なひとをもっと大切にできるように、かけがえのない大切なひとが自分らしくいきていけるように、そのための仕組みをみんなでつくる』という目標を持って、医療の枠組みを飛び越えたビジネスモデルにチャレンジする。結果、それがヘルスケアにおける社会課題の解決につながる。このようなチャレンジをできていることが、弊社の魅力ではないかなと思っています。
―PHRサービス事業協会との関わりは?
山東:シミックホールディングスが、PHRサービス事業協会の立ち上げ企業だったことから、その流れで弊社も参画したというのが表向きの経緯です。裏テーマではないのですが、協会活動に参加している期待は、企業同士の協業と国の施策との連携によるイノベーションです。先ほどご紹介した運輸業向けの事業も、国土交通省の運輸安全マネジメント制度という制度とPHRサービスをマッチングさせたことで成果が得られ始めています。現在、健康経営の推奨などの国の施作が日々進んでいますが、やはり国との動きと連動することが重要だと感じます。PHRサービスは社会制度になり得る事業ですし、PHRサービス事業協会も、経済産業省の動きの一つとして発足したので、経済産業省が推奨する社会制度に発展する可能性も高い。PHRサービス事業を生業としている弊社にとっては、その会員であるメリットは大きいと考えて現在協会の会員企業の皆さまと一緒に汗を流している状況です。(笑)
―この機会に、現在PHRサービス事業協会への入会を検討されている企業の方々へメッセージなどあればお聞かせください。
山東:PHRサービス事業の場合、手を組んだ方が良いことがたくさんあります。1社で、日本の中で新しい概念を定着させようとすると限界があります。旧態依然の概念を壊していく、またはリニューアルをかけていく時には、協会が非常に重要な役割になってきます。例えば、弊社が取り組んでいる運輸業との取り組みですが、他社さんにも真似てください、パクってください、じゃんじゃんやってください。そうすることでムーブメントを作り、そこから行政とのバランスを整えていかないと、PHRサービス事業のマーケットは開きません。なので、ライバルではなく同業者として一緒にやることで、大きな風穴を開けていきたいです。これは他の業種や業態の企業さんも同様だと思うので、多くの企業に参画していただくことで、ユニークなPHRサービス事業がどんどん出てくれば、日本のヘルスリテラシーも高っていくはずです。ご入会、お待ちしています。
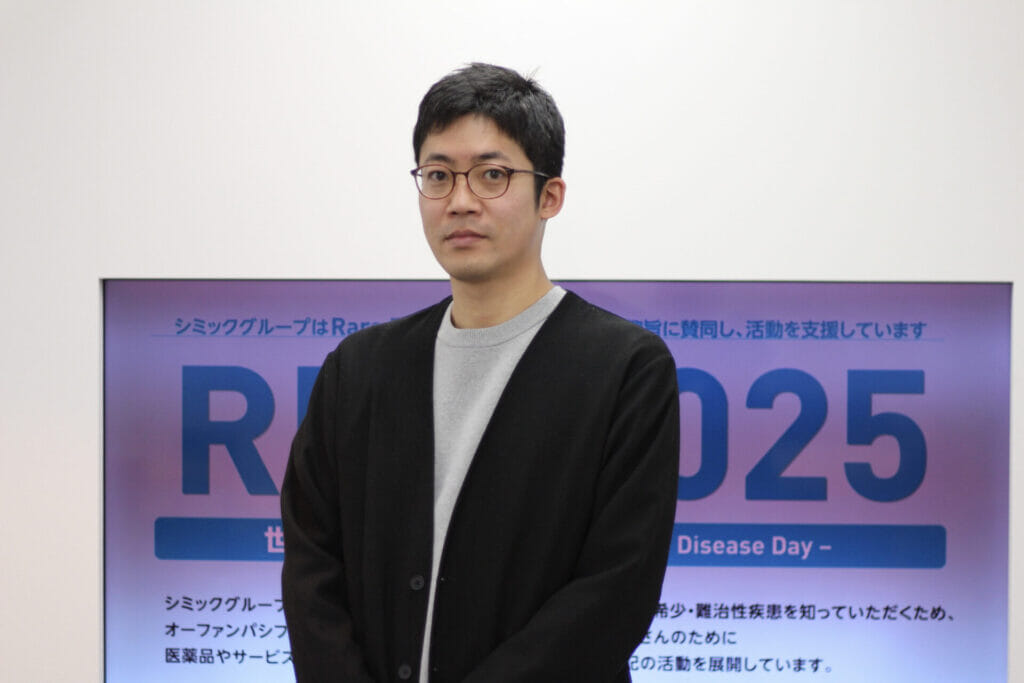
ーお忙しい中、ありがとうございました。
harmo株式会社
https://www.harmo.biz
〒105-0023東京都港区芝浦1-1-1
個人やご家族が個々の医療・健康情報を活用可能にするスマホアプリケーション「harmoおくすり手帳」を基盤としたサービスを展開。専用ICカードを合わせ約44万人の利用者を擁し(2024年1月現在)、全国2万軒以上の薬局で利用実績がある。また、川崎市・神戸市・豊中市・さいたま市・滋賀県などでは、地域の薬剤師会と協業し、地域住民の健康増進に資する活動を展開。
<「harmoおくすり手帳 for Driver」について>
ドライバーの治療継続と適切な服薬をサポートする運輸企業向けの健康支援サービス。ドライバーは「harmoおくすり手帳」アプリを通じて服薬情報を記録し、会社は開示許可を得て服薬情報をharmoシステム上で管理することで、ドライバーの通院や服薬状況を確認できます。2024年12月には、本サービスを導入した三和運輸機工株式会社が国土交通省「運輸安全マネジメント優良事業者等表彰(危機管理・運輸安全政策審議官表彰)」を受賞。
harmoは、本サービスの提供を通じて、運輸業界の安全性向上と、疾患を抱える高齢ドライバーの方も安心して長く活躍できる職場環境の実現を目指している。
【サービスサイト】
https://www.harmo.biz/well-harmo/
【資料ダウンロード・お問合せ先】
https://www.harmo.biz/well-harmo/#well-harmo-contact
山東 崇紀(Takanori Sando)
harmo株式会社代表取締役 Co-CEO
健康を気遣い始めたこと:形状記憶腹筋ダイエットで一気に2.5kgの減量に成功。その際、サポートしてくれた社内のスタッフが多忙となり、現在はひとりで悪戦苦闘している