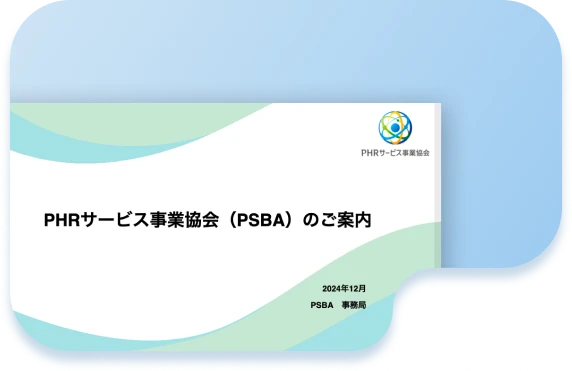PHRサービスの事業化・社会実装を実現するためには、多くの知恵を集めることが必要。そのための仲間は多ければ多いほど良い。
2025.03.19
今回はライフネット生命保険株式会社 松浦勉様にお話を伺いました。

松浦 勉 (Tsutomu Matsuura)
ライフネット生命保険株式会社 執行役員 【担当】CXデザイン部、お客さまサービス部、保険金部
現在行っている健康法:自宅近くに畑を借りて家庭菜園を行い、休日は太陽の下で体を動かしている。一昨年フルマラソンに初挑戦。以来毎年出場を続けている。
お客さまや社会に対して正直な会社でありたい。生命保険をもっとわかりやすくしたい、保険料を安くしたい、もっと手軽で便利にしたい。

―はじめに、ライフネット生命の事業内容について教えてください。
松浦様:当社は主にインターネットを通じて、保険の販売、契約の維持管理、保険金等の支払いを行なっております。2006年10月に、お客さま視点の新しい保険会社を目指して準備会社として設立されました。そして、2008年5月に生命保険会社として開業しました。
開業以来、「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」を「ライフネットの生命保険マニフェスト」として掲げています。情報公開を徹底してお客さまや社会に対して正直な会社でありたい、生命保険をもっとわかりやすくしたい、保険料を安くしたい、生命保険をもっと手軽で便利にしたい。そのような思いで、日々事業活動をしています。おかげさまで2025年のオリコン顧客満足度(R)調査で生命保険総合1位となっています(https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/202501-06-news.pdf)。
―たしかに、御社の設立も契機の1つとして、近年、生命保険の在り方が大きく変わってきたのを感じています。松浦様はいつ頃からライフネット生命で働いていらっしゃるのでしょうか。
松浦様:入社は2010年、ライフネット生命の設立から2年後というタイミングです。それまでは同業他社におりました。当時、個人的にもさまざまなECサイトを使い始めていて、社会全体でインターネットサービスがどんどん伸びていく中で、生命保険も例外なくEC化が進んでいくだろうということを肌で感じていました。「自分もそこで新しい挑戦がしてみたい!」、と思い、転職しました。
―御社ならではの、社員に向けた福利厚生や健康管理の取り組みがあれば教えてください。
松浦様:当社の「ナイチンゲールファンド休暇」という制度は、かなりユニークだと自負しています。
当社は、2016年にライフとワークのバランスがとれて、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる組織づくりを目的として『ライフサポート休暇』という制度を新設し、その制度における一つの具体的な休暇として従業員本人だけでなく家族・パートナーが病気やケガになったときの看護を目的とした「ナイチンゲール休暇」を設けました。この休暇は、家族だけでなく、パートナーなどの大切な人の看護が必要なときや、自分が病気やケガをしたときにも利用できるもので通常の年次有給休暇とは別に、年3日分付与される特別有給休暇です。
現在の「ナイチンゲール休暇」の取得率は2023年実績で53%となっており、社員の中には「ナイチンゲール休暇」を使う機会があまりない人もいます。この未使用になった休暇も、ライフネット生命では有効活用をしています。そのしくみが、「ナイチンゲールファンド休暇」です。
「ナイチンゲールファンド休暇」は、会社全体で未使用になっている「ナイチンゲール休暇」を会社側が積み立てておき、社員のいざというときに備えておきます。社員ががんなどの大きな病気により検査通院や入院準備などが必要となった場合に、積み立てておいた休暇から10日間の特別有給休暇が付与されます。年次有給休暇の有効期限は2年間ですが、たとえばがんのような重篤な病気が疑われるとさまざまな検査をして診断が確定するまでに時間がかかり、治療にはさらに多くの日数が必要です。入院や手術ということになればまとまった休暇が必要になります。休職になる前に治療スケジュールや本人の意向を確認するための時間を確保できるよう、社員どうしの助け合いの制度として設けた特別な休暇制度です。
―みんなでリソースを出し合って、困っている人を助けるというわけですね。
松浦様:はい、そもそも当社が扱う生命保険とは、お互いが助け合うという相互扶助の仕組みで成り立っています。この仕組みを自社の人事制度に応用し、社員がお互いに支え合う制度をつくりました。
―素晴らしい制度だと思います。社員の皆さまの反応はいかがですか。
松浦様:人事総務部によると、社員からは「こういった休暇があることで、安心して働ける」「保険のような助け合いの精神のある休暇で素敵」などの声があがっています。これはまさに当社が生命保険の提供を通じて社会に提供していく価値です。喜んでもらっているのは嬉しいですね。
保険ビジネスはPHRサービスとの親和性が高い。協会への参加を通じて、より良いサービスを開発したい。

―では、御社が当協会に入会された経緯や動機・理由について教えてください。
松浦様:協会の中心となって取り組んでいらっしゃるエーザイ株式会社さんから、ご案内いただきました。当社は現時点ではPHRに関連したサービス・取り組みを行っているわけではないのですが、お話を伺って、保険ビジネスとの親和性が高いPHRやPHRサービスに対する知見を深めるとともに、ネットワークづくりが出来ればと思い、設立時に入会いたしました。
―PHRと保険ビジネスとの親和性、もしくは御社との親和性について、詳しくお聞かせください。
松浦様:たとえば、2023年4月に保険業界全体(一般社団法人 生命保険協会)として、『デジタル社会における生命保険業界の将来 ~マイナンバー制度を通じたデータ利活用による生命保険の利便性向上に向けて~』という報告書・提言書を発表しています。これは、日本におけるマイナンバーカードの急速な普及や関連サービスの充実等を踏まえ、諸外国におけるデジタル活用の事例を参照しつつ、マイナンバー制度を通じたデータ利活用による効率的・効果的な新たな生命保険関連サービス提供の可能性を検討し、その実現に向けて具体的な提言を行ったものです。提言のポイントは主に2つです。1つは、電子証明書機能の全スマートフォンへの搭載の早期実現など、マイナンバーカード・公的個人認証サービス・マイナポータルの機能向上。もう1つは、公的な個人認証サービスやマイナポータルにおいて医療保険情報、診断情報等のデータ連携範囲を拡大することです。これによって、保険業界全体として、皆さまにより良いサービスをお届けしていきたいと考えています。
中でも当社は、生命保険をインターネットを通じて販売していますので、こうしたデータ連携の取り組みについて、他社さま以上に親和性が高いと考えています。こうした文脈において、PHRサービスの開発とPHRの活用を検討しているところです。
―新たな領域への取り組みという点では、他社とのネットワークづくりも重要なポイントになるでしょうか。
松浦様:そうですね。本当に皆さまのお役に立てるPHRサービスとはどのようなものなのか。これを追求し事業開発していくのに、自社内だけで進めるのは難しい。協会の活動に参加することで情報を得たり、参加している皆さまとの繋がりをつくっていったりすることが必要です。協会を通じたネットワークをもとに、共創につなげていければと期待しています。
―そうしたご期待に対し、これまで活動してきて当協会をどのように評価されていますか。
松浦様:現在は標準化委員会とサービス品質委員会に参加し、月1回ほどの定例会合にはできるだけ参加するようにしています。基本的な知見を1つひとつ得ていくことから始め、いずれ当社から協会や社会に価値を提供できるようにしていきたいですね。
ネットワーキングについては、昨年のイベントでは色々な方とお話させていただけて、とても有意義でした。手ごたえを感じていますので、今後はより積極的に、できるだけ多く参加して、色々な方と繋がっていきたいと思っています。
―では最後に、PHRサービス事業協会入会を検討されている企業様・担当者様に向けたメッセージをお願いします。
松浦様:きわめて専門性の高い団体だと思われがちかもしれませんが、PHRサービス事業協会には当社のような、現時点ではPHRに直接は取り組んでいない企業も参加しています。あまり身構えずに、お気軽にご参加いただければと思います。
今まで協会の活動に参加してきて、現在のPHRサービスの課題の一つがマネタイズだと感じています。協会の皆さまも同じ認識だと思いますので、さまざまなお立場の多くの皆さまと知恵を出し合い、PHRサービスの事業化・社会実装を実現していきたいです。そのための仲間は多ければ多いほど良い。ぜひご参加ください!
ライフネット生命保険株式会社 (URL: https://www.lifenet-seimei.co.jp/)
〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル8階
「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念のもと、一貫してお客さま視点に立った生命保険を提供。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指している。