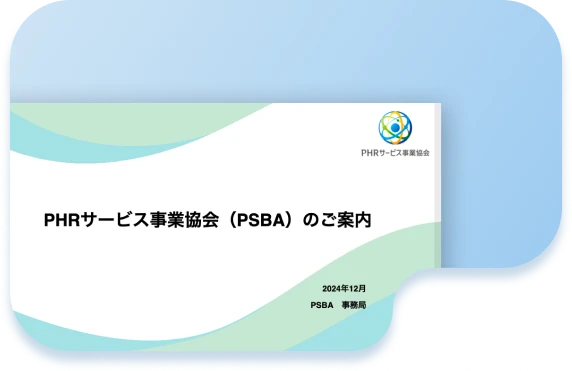社会全体の健康寿命を延ばすためには、業界を超えた情報交換と共創を進めることが重要です。
2025.03.03
今回はレイ・フロンティア株式会社田村建士様にお話を伺いました。

田村建士(Kenshi Tamura)
レイ・フロンティア株式会社 代表取締役社長 CEO
現在行っている健康法:自社のライフログアプリを活用して、運動量や睡眠を日々チェック。運動不足の際には水泳をしている。食事管理を兼ねた料理も趣味。
当社は、ライフログアプリの開発・運用を通じて、ユーザーが継続的に生活情報を記録しやすくなる仕組みや技術を持っています。

― はじめに、御社の事業内容について教えてください。
田村様:当社は2008年創業のスタートアップで、位置情報サービスを活用したデータ解析やソフトウェアの開発・運用などが主な事業です。私たちは、自社開発のスマートフォンアプリを通じて、累計100万人以上の行動データを収集し、それを分析する独自のAI技術を持っています。近年は、これをライフログ(日々の生活や体験をデジタルデータに残していくこと)の分野に応用し、個人の健康管理をサポートするサービスを開発する事業に注力しています。
― スマホのデータから行動を分析して健康アドバイスや運動の提案などをアウトプットする、というようなイメージでしょうか。
田村様:その通りです。ユーザーの行動データからパターンを解析した上で健康管理や行動変容のサポートに繋げていくサービスを、法人のお客様に提供しています。当社は、お客様の課題整理・目標設定からスマホアプリの開発、データの分析・活用までを一気通貫でご提供し、上流から下流まで伴走できることが強みです。「目標はあるが、どのように進めるべきか分からない」というご状況の企業様に対しても、課題を明確化し、それを実現するための解決策をご一緒に見つけ出していきます。
― 位置情報を活用したサービスというと、商業施設のマーケティングや街の活性化、あるいは従業員の行動管理などに使われるケースが多いように思います。御社が健康サービスにフォーカスしている経緯・理由について教えてください。
田村様:おっしゃる通り様々な活用法がある中で、近年健康関連分野のお客様のニーズが高まってきたので結果的に注力することになったという感じです。この流れのきっかけとなったのが2018年頃から携わらせていただいている宇都宮市様の健康ポイントアプリです。これは活動量に応じてポイントを付与するサービスですが、実はポイントを付与するだけではなく、移動データを精密に取得して分析し、二次データの活用も行っています。このプロジェクトがきっかけとなって、多くの健康サービス関連の企業様から引き合いをいただくようになりました。
ユーザーの生活や活動量を把握し、それを踏まえて行動変容を促していくサービスを開発するためには、まず何よりもユーザーの生活データを取得することが必要となるのですが、この、データを取るというプロセスの設計が難しいんです。それに対し当社の「SilentLog(サイレントログ)」は、もともとB to C向けのライフログアプリとしてスタートしました。この経験を活かし、ユーザーが継続的にデータを記録しやすくするノウハウを蓄積し、現在はB to Bの分野に応用しています。この点をご評価いただき、多くの企業様にお取り引きいただいています。
― なるほど、御社の強みと健康関連サービスとの相性の良さがよく分かりました。ところで田村様はレイ・フロンティアの創業から数年後にジョインされたとうかがっています。その経緯を教えてください。
田村様:創業者で現在は取締役CTOの大柿とは、前職で先輩・後輩だったんです。私たち自身は「一緒に創業した」という感覚なのですが、たまたまタイミングとして大柿が先に起業して、私が少し後から入ったというかたちになりました。
私は元々、土木工学のエンジニアで、構造計算や都市開発などの領域で活動していました。当時、2000年代前半から中盤にかけては土木の世界でもデジタル化がどんどん進んでいった時期で、スマートフォンもその頃登場しました。そうした流れをみていて、「これからリアルの世界はどんどんデジタル化していくだろう」と思ったんです。そしてそのハブとなるのは、人間の身体に密着しているスマートフォンというデバイスではないか、と。この領域のビジネスは今後必ず伸びていくだろうと思いましたし、いちエンジニアとして、技術の発展や変化が大きいところでチャレンジしたいという気持ちもありました。そこで、この会社を始める決意を固めました。
― 御社は健康関連サービスの開発・運用をされていますが、現場はどうしても時間や作業量に追われ多忙になりがちかとも思います。社員の健康管理や福利厚生などについて、どのような取り組みをされていますか。
田村様:無理なく続けられる就業環境づくりを大切にしています。当社はリモートワークが多く、かつ結構ゆるいフレックスタイム制を導入しています。出来る限り自主管理が出来る環境をつくることに努めており、社員を「時間」で縛るのではなく、「成果」で評価しています。体調が悪ければ休んでいいよ、と。当社はエンジニアの会社なので、資産の中で「人」の割合が高い。ですので、社員の健康状態の維持は重視しています。健康診断もかなりしっかりとやっていますし、コロナやインフルエンザのワクチン接種費用を会社が負担するなど、力を入れています。
私たちの技術は、健康の専門家と組むことで初めて世に出ていける。協会での活動を通じて、皆さまとご一緒に発展していきたい。

― では、ここからはPHRやPHRサービス事業協会についてのお話をうかがいます。まず、ご入会された経緯について教えてください。
田村様:お取引先の企業が多く入会されていて、PHRについてリサーチを進める中で、PHRサービス事業協会の存在を知りました。PHR市場が急速に成長する中、データの標準化や業界全体のルールづくりの重要性がますます高まっています。当社の技術をより広く活用し、業界の発展に貢献するため、マーケティングチームと相談の上、入会を決めました。
― 入会の具体的な理由はどのようなものだったのでしょうか。また、今後どのような活動をしていこうとお考えですか。
田村様:個人の健康データはとてもセンシティブな領域のデータですので、データの標準化や業界全体のルールづくりが非常に大事だろうと思っております。その点で、大手企業、スタートアップから所管の官庁まで多様な皆さまが集まっている協会の存在は、とても重要です。
また、当社が扱っている位置情報や移動の情報は健康に関わる事業者にとって根本・核となるものです。当社の技術は、PHR関連事業者だけでなく、健康サービス・自治体・製薬企業など、さまざまな分野と連携が可能です。データ活用を通じた健康支援に貢献するため、協会の皆さまと新たな価値を共創していきたいと考えています。一方で、当社内には健康に関する専門家はいませんので、そういった点を協会を通じて補完できればとてもありがたいです。私たちの技術は、健康の専門家と組むことで初めて世の中に出ていける、世界の発展に寄与できるようになります。協会での活動を通じて、皆さまとご一緒に発展していければ嬉しいです。
― 標準化やルール作り、そして技術系プレイヤーと医療・健康系プレイヤーの連携。重要な視点を示していただきありがとうございます。その他に具体的に期待している活動はありますか。
田村様:異業種連携を含めた協会内のコラボレーションにも、とても期待しています。当社はPHR以外の領域の団体にもいくつか加盟していますが、メンバー間のコミュニケーションを活発化させて世の中に見せていけるものをどれだけ創っていけるかということが、こういう団体にとってとても重要だと感じています。
― おっしゃる通りですね、そうした活動を1つひとつ増やしていきたいと思います。
では最後に、PHRサービス事業協会に入会を検討されている皆さまに向けたメッセージをお願いいたします。
田村様:今後、日本はもちろん多くの先進国で高齢化社会が進み、高齢者も働かなくてはいけない社会になっていきます。一人ひとりが健康状態を維持することが、本人にとっても社会にとっても今以上に重要になります。自己管理が重要な時代に、各社の技術を組み合わせることで、新たな健康維持の仕組みを創出できるはずです。これからの時代では、言わば「学習」と同じようなスタンスで「健康」が重要視されてくるでしょう。各社の専門性や技術を結集し、社会全体の健康寿命を延ばすには、情報交換や共創を積極的に進めることが不可欠です。1人でも多くの方に入っていただくことで、成功の可能性が高まっていくと思います。ぜひご一緒いたしましょう。
レイ・フロンティア株式会社
人工知能による位置情報分析プラットフォーム「SilentLog Analytics」の開発・運営を行う。独自の移動データの収集・推定技術を強みとし、サービスの企画提案、アプリ及びシステム開発・運用を企業に提供。『仮想と現実をつなぐ世界一のサービスを作る』というビジョンのもと、世界的にも類のない行動分析企業になることを目指している。